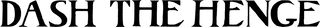ケイティ・J・ピアソン
サウンド・オブ・ザ・モーニング
ケイティ・J・ピアソンは、彼女がカントリー歌手ではないことを知ってもらいたいと思っています。確かに、現在26歳のピアソンの有名なデビュー作『リターン』にはこのジャンルの影響があった。ピアソンがブリストリアの新人から批評家から絶賛されるブレイクスルースターへと雪だるま式に成長し、イギリス全土でショーをソールドアウトさせたアルバムだ。しかし、彼女の高揚するワイドスクリーンのメロディーと温かく親密なストーリーテリングの魅力的なブレンドには、単なる 3 つのコードと真実以上のものもあります。
「最初にラインダンスをしたり、ラインストーンを着けたりして作った(『Tonight』の)ミュージックビデオが1つありました。そこから、それが本物のものになったのです」と彼女は笑う。 「どのレビューも「カントリーっぽい」ものですが、実際にはレコードには文字通りカントリーソングが 1 曲ありました。でも、それが新しいレコードの良いところだと思うし、それは人々が私に期待するものではないと思う。新しいアルバムはどんな感じかと聞かれると、ちょっと…ちょっと違う?!」
タウンズ・ヴァン・ザント、エルトン・ジョン、フガジの優劣を同列に叙情的に語ることを喜んでいるピアソンの音楽パレットには常に多くのことが起こっている(参考までに、彼女は自分のデビュー作をフォーク・ロックのLPと呼ぶだろう。何でも)。しかし、批評家たちは2020年11月にHeavenly Recordsからリリースされた『Return』の詳細を歪めていたかもしれないが、それでもこのアルバムに対する称賛は殺到していた。これまでメジャーレーベルのプロジェクトを通じてこの業界を味わっていたが、すぐに評判が悪くなってしまった。今回の違いは明らかだった。タイムズ紙は「ケイト・ブッシュとドリー・パートンの出会いの驚くべき質のヴォーカル・デリバリー」を賞賛し、DIYとリード・シングル「テイク・バック」では「あらゆる瞬間に人間らしさを見出している」と評価した。ガーディアン紙で「ザ・ラジオ」は「純粋な喜びの叫び」と評されたが、ロックダウンによる暗い犠牲のさなか、この奇妙にも楽観的なアルバムの何かが本当に共鳴し始めた。
「8年間音楽を作り続けて、デビュー作をリリースするところまで来るのは恐ろしかったです、すごい!」彼女は大袈裟に顔をしかめながら言う(ピアソンの逸話では、ランダムな騒音や興奮する身振りは当然のことである)。 「しかし、奇妙なことに、他の時期にはリリースできなかったような気がします。 (ロックダウン中に)人々が私に言っていたすべてが、そのアルバムを書いたときに私が感じていたすべてであるように感じました。これは私にとって非常に個人的なアルバムで、多くの人が家にいて孤独を感じていた時期にリリースされました。それは多くの人々の命を奪う解毒剤でした。」
彼女の最初のアルバムでちょうどいいタイミングで聴覚に潤いを与えたので、その次のアルバムが好奇心に満ち、活動を再開し、視野を広げようとしている世界を反映するものであることは適切であると感じます。ここ数カ月間のピアソンの課外活動が、オーランド・ウィークスの最新アルバム『ホップ・アップ』にゲスト・ヴォーカルを提供するなど、彼女がさまざまなジャンルに足を踏み入れることができることを示したとすれば。エンド・オブ・ザ・ロード・フェスティバルでヤード・アクトとコラボレーションするために現れた。トラッドフォーク集団ブロードサイド・ハックスの2021年プロジェクト「ソングス・ウィズアウト・オーサーズ」で歌っているが、近々リリースされるセカンド・アルバム「サウンド・オブ・ザ・モーニング」ではその精神を引き継いでいる。それは依然としてケイティ・J・ピアソン(つまり、楽々と魅力的で、心豊かで、その比類のないボーカルによって舵を切られている)ですが、ケイティ・J・ピアソンが音楽的にも叙情的にも新たな領域に自分自身を押し込んでいるのです。
この曲は、散歩したり、毎日冷水で泳いだり、「とにかくすごくリラックスした」という自己規定のダウンタイムを経て、2021年後半に書かれレコーディングされたもので、「サウンド・オブ・ザ・モーニング」のクレジットでさえ、歌手の新たな実験への渇望を告白している。 。今回『リターン』プロデューサーのアリ・チャントのデスク業務に加わったのは、スピーディ・ワンダーグラウンドのヘッド・ホンチョ、ダン・キャリーで、アルバムのより荒々しいトラックのいくつかでピアソンと協力した。 「ダンは私から全く異なる構造的でソングライティングのスタイルを引き出してくれました。それが私が望んでいたものでした。もう少し自信を持って、人前で言えるものです」と彼女はうなずいた。 「彼は私の中に領域を広げたいと思っている部分があることを察知していました。私はそれをどこでどこまで押し進めるべきか分かりませんでしたが、それはまさに私が探していた種類の進歩でした。」
「Alligator」を支え、カタルシスをもたらすコーラスを相殺する、ずるずると進むベースリフはその好例である。 「その日はE.ONの500ポンドという高額な請求書を支払わなければならなかったので、とても機嫌が悪かったです。私は父に電話していて、「お父さん!」って感じでした。めちゃくちゃだったわ!」と彼女は思い出す。 「私はスタジオに入ってすぐに泣き出しました。そしてダンは『とにかく曲を書こう』と言ったんです。私たちはこの本当にジャンキーなものを書き始め、それが『アリゲーター』の始まりとなりました。」